粘土を造るところから作陶が始まります。
地元の土と釉薬を使い、手作業で器を作る。
今も昔も変わらないこだわりがあります。
-
①「土造り1」
台原(仙台市青葉区)の粘土層から掘り出した土を使用して器を作っています。
そのままでは作陶に使用できないので、工程を重ねて粘土に精製していきます。
・敷地に運んだ土を細かく掘り出します。
・ミキサーで攪拌・粉砕して土を溶かします。
・網で濾して木の根や石などの不純物を取り除きます。


-
②「土造り2」
・泥状の土を水槽に溜め込み、沈殿させてねかせます。
・比重の違いで土と水が分離するので、上澄みだけを取り除きます。
・残った土を鉢に入れて数日陰干しさせ、余分な水分を飛ばします。
・適度な硬さになったら土練機に通し、室(むろ)で保管します。


-
③「土練り」
成形を行う前に粘土を練ります。
練ることで成形しやすくなり、後の工程でひび割れが発生するのも防ぎます。
・粘土の内側と外側の硬さを均一にします。
・粘土の粒子を整え、中の空気を抜きます。
・練り終えた粘土を砲弾状にまとめます。
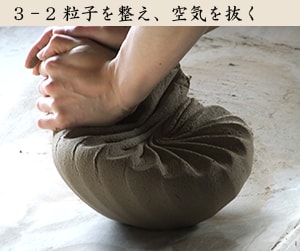

-
④「成形」
主に制作している食器類は、電気ロクロを使用して成形します。
・粘土を上げ下げして芯(中心)を出します。
・適量の粘土を取って挽いていきます。
・挽き終えた器をしっぴき(糸)で切り離します。


-
⑤「高台(こうだい)仕上げ」
器を適度な硬さに乾燥させた後、伏せて高台を削りだします。
・ロクロの天板にシッタ(円筒)を備え付けます。
・伏せた器をシッタに固定し、カンナで削っていきます。
・高台裏に判子を押します。


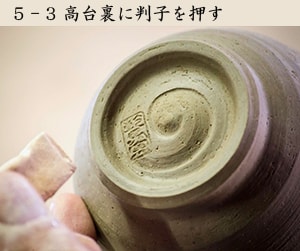
-
⑥「乾燥」
粘土は水分が残った状態で焼成すると割れてしまうので、十分に乾燥させます。
食器などの小さい器は1週間程度乾燥させます。
大きい作品は1ヶ月以上かけてゆっくりと乾かします。



-
⑦「素焼(すやき)」
800度前後までゆっくりと焼成します。
焼成後は常温になるまで数日待ち、中の器を取り出します。
素焼を行うことで、釉薬を掛ける際の型崩れを防ぎます。
また、素地への釉薬の定着も良くなります。
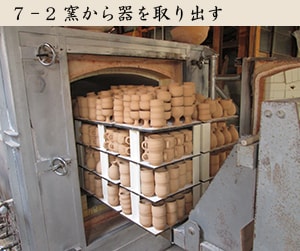
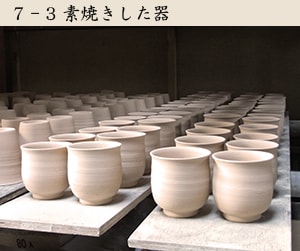
-
⑧「釉薬(ゆうやく)調合」
本焼で必要となる釉薬を調合します。
・鉱物や金属など、様々な原料を計算した調合比率で混ぜ合わせます。
・ポットミルで攪拌・粉砕します。
・網で濾して細かな不純物を取り除きます。
堤焼の代表的な釉薬である海鼠釉(なまこゆう)は地元で採れる原料を使用しています。
・鉄分を多く含んだ川端の岩
・お米の籾殻灰...など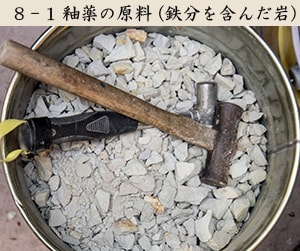

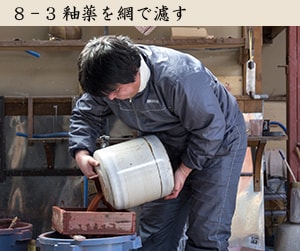
-
⑨「釉掛け(くすりがけ)」
素焼の器に釉薬を掛けます。
釉薬を水と混ぜ合わせ、適度な濃さに調節して器に掛けていきます。
堤焼の海鼠釉の場合、2種類の釉薬を掛けます。
黒の釉薬を掛けて数日乾燥させた後、白の釉薬を掛けます。


-
⑩「本焼(ほんやき)」
一日かけて1250度前後まで焼成します。
焼成後は常温になるまで数日待ち、中の器を取り出します。
釉薬は粘土の表面と溶け合い、ガラス質となって水分の浸透や汚れを防ぎます。
また、釉薬の濃淡や温度の強弱によって器の表情が変化し、それぞれに個性が生まれます。


-
⑪「ハマすり」
釉薬を掛けていない高台部分はザラザラしており、テーブルなどに傷がついてしまいます。
そのため、最後に高台部分を削ります。
・砥石で削って表面を滑らかにします。
・ガタつきを砥石で修正して水平にします。
・傷や割れをチェックし、完成となります。




